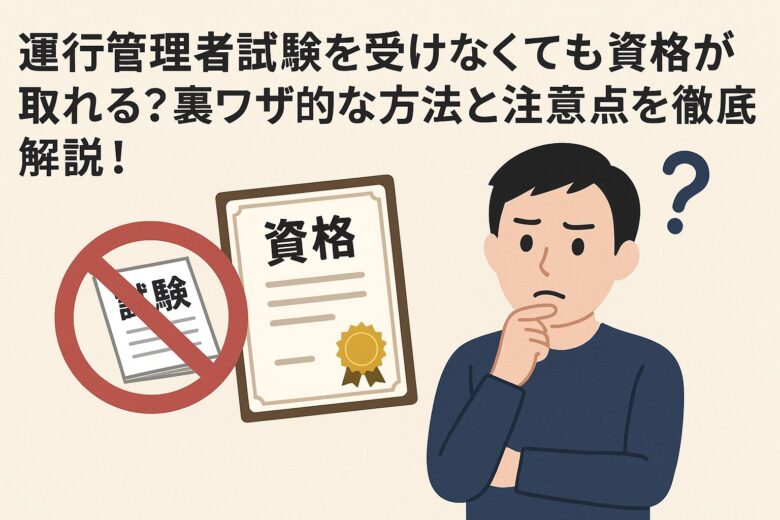運行管理者資格と言えば、国家試験に合格するのが一般的なイメージですが、実は「試験なし」で資格を取得する方法もあるんです。
特に補助者としての実務経験を積んだり、一部の職種で例外的に認められる場合には、試験を受けずに資格者証を交付できるルートがあります。
ここでは、試験なしの2つのルートや、それに関わる講習の仕組みも整理していきます。
「本当に試験なしでOKなの?」と不安な方にとって、具体的で正確な情報をお伝えします。
運行管理者の実際の求人や給料の相場はドラEVERで見つけることができます。
・ドライバーの専門特化サイトです
・実際のトラックや会社の写真も見れます
・10秒で簡単登録
・もちろん無料で利用できます
※登録後に「運行管理者」で絞り込み検索してください。
その他のドライバー職やキャンペーンもすべて利用できるようになります。
試験なしで資格取得できる「2つのルート」とは?
実は運行管理者の資格は、国家試験を受けなくても、以下の2つのルートで取得可能です。
いわゆる“抜け道”ではなく、法律で認められた正当な方法なので、条件を満たせば誰でもチャレンジできる制度です。
1. 補助者としての実務経験+講習ルート
- 運行管理補助者や代務者として、5年以上の実務経験を積む
- その間に国交省指定の講習を5回受講し、少なくとも1回は「基礎講習」を修了する必要あり
- 実務経験と講習の両方の要件を満たせば、運行管理者試験なしで「資格者証」の交付を申請できます
このルートでは、「試験を受けずに資格を手にできるが、手続きは講習と実務で裏打ちされた“実力証明”」となります。
2. 一部例外職種からの申請ルート
- 特定の職種に従事していた場合、実務経験の一部免除などの特例が認められる場合も。
- 例として、旅客輸送業での運行管理補助者経験がある人が貨物への流用を希望するなど、限定的なケースがありますが、一般的な取得方法ではありません。
- 基本的には①の講習+実務経験ルートが主流となります。
ポイントまとめ
| ルート | 主な条件 | 試験の有無 |
|---|---|---|
| 補助者+講習 | 5年の実務経験+講習5回(うち基礎講習1回以上) | 不要(講習と経験で可) |
| 職種例外 | 特定職種での経験・法令上の特例 | 状況による(試験免除要件) |
「試験なし取得」は決して簡単ではなく、しっかりした経験と講習の積み上げが必要です。
そもそも運行管理者資格とは?役割と重要性を再確認
運行管理者資格は、ドライバーや車両の安全管理を行う“国家資格”。道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づき、運送会社の営業所には必ず配置されなければならない重要ポジションです。
運行管理者の主な役割は以下の通りです。
- ドライバーの乗務割とスケジュール作成、過労防止のための勤務管理
- 点呼実施(乗務前後・中間点呼)によるドライバーの健康・アルコールチェック
- 休憩・睡眠施設の管理や適切な休憩の指示など、安全運行を支える設備管理
- ドライバーへの業務指導・法令指導や安全教育
- 運行計画・ルート選定、悪天候や交通規制時の指示・ルート変更対応
- 経営者への 安全改善の助言 や運輸安全マネジメントへの参画。
このように、運行管理者はドライバーと車両の安全運行を保証する担い手であり、事故や過労などの重大リスクを防ぐ最終ラインの役割を果たしています。
運行管理者の合格率が低い理由に関しては、こちらの記事で詳しくご紹介していますのでご覧ください。

講習だけでOK?基礎講習と一般講習の違い
運行管理者資格を試験なしで取得するには、講習を正しく選んで受講することが不可欠です。
基礎講習と一般講習の内容や目的は異なるため、どちらが必要なのか、よく理解して進めていきましょう。
基礎講習とは?
基礎講習は、運行管理者資格の受験資格を得るため、または補助者としての就任に必要な講習です。
- 法令と運行管理の基本知識を3日間・約16時間かけて学びます。
- 修了後は、運行管理者試験の受験資格が得られるほか、補助者として選任可能になります。
- 受講料は約8,900円、開催日程は全国で随時案内されています
一般講習とは?
一般講習は、すでに資格を持った運行管理者や補助者が定期的に最新知識をアップデートするための講習です。
- 法令や業務内容、安全管理の最新情報などを1日・約5時間かけて学びます。
- 新たに選任された場合や、選任者は原則年度内に受講が義務付けられています。
- 既に選任されている資格者は、2年に1回の受講義務があります。
- 受講料は3,000〜3,200円程度
比較表:基礎講習と一般講習の違い
| 項目 | 基礎講習 | 一般講習 |
|---|---|---|
| 対象者 | 試験受験希望者 / 補助者希望者 | 選任後の運行管理者・補助者 |
| 目的 | 資格の基礎知識習得と補助者選任 | 最新知識の取得と法令順守 |
| 受講時間 | 約16時間(3日間) | 約5時間(1日) |
| 受講頻度 | 必要に応じて一度 | 2年ごとに1回必須 |
| 受講費用 | 約8,900円 | 約3,000〜3,200円 |
資格者証交付申請の流れと注意点
運行管理者資格者証を取得するには、試験合格者も講習+実務ルートでの取得者も、必ず運輸支局へ申請手続きが必要です。
申請を忘れるとせっかくの努力が無効になってしまうので、手順と注意点をしっかり押さえておきましょう。
必要書類と提出方法
申請に必要な書類は以下の通りです(貨物用の場合)
- 運行管理者資格者証交付申請書(業態ごとに様式が異なるため注意)
- 収入印紙 270円分(超過貼付の場合、欄外に「過納承認」と署名が必要)
- 本人確認書類:運転免許証の両面コピーまたは住民票(マイナンバー記載なし)
- 試験合格通知書(試験ルートの場合)
または実務経験・講習証明書類(講習+実務ルートの場合) - 返信用封筒(角2サイズに切手と宛名を忘れずに)
提出は窓口持参または郵送のどちらでも可能です。
郵送時は簡易書留扱いで、封筒に「A4が入るサイズ」「追跡可能」「440〜530円切手貼付」などの指定があるのでご注意ください。
資格者証交付申請の流れと注意点
試験ルート・実務+講習ルートのどちらでも、資格者証を取得するには運輸支局への申請が必須です。
申請漏れや期限切れにより、せっかくの取得条件を逃してしまうこともあるため、流れをしっかり押さえておきましょう。
必要書類と提出方法
申請に必須の書類は以下の通りです。
- 運行管理者資格者証交付申請書(業種:貨物/旅客で別用紙)+収入印紙 270 円。
- 本人確認書類(運転免許証または住民票(マイナンバー記載なし))
- 試験合格者:合格通知書原本/実務+講習者:実務経験証明書+講習受講証
- 返信用封筒(A4用、簡易書留用切手440~530 円貼付)
郵送申請も可ですが、簡易書留での郵送や封筒サイズ・切手金額にルールがあるので要確認です。
実務経験や講習の勘違いに注意!
- 補助者としての実務経験は基礎講習修了後の経歴のみカウント。
- 講習は1年度内に複数回受講しても1回分にしかならないルールです。
- 郵送先の支局は、住所地や合格地の管轄運輸支局で対応が異なる場合があるため確認を。
申請期限と交付までの期間
- 試験合格者は合格日から3ヶ月以内が申請期限で、それを過ぎると資格が無効になります。
- 申請受付から約1~1.5ヶ月で資格者証が交付されます。年度末は混みやすいため余裕を持つのが◎。
注意ポイントまとめ
- 収入印紙は270 円ぴったりが望ましく、超過の場合は余白に「過納承認」と署名が必要です。
- 記入は消せないボールペンで、記入例に沿って正確に記載しましょう。
- 返信用封筒の添付・切手貼付忘れに注意(郵送希望時)。
- 書類不備や期限超過では申請却下や資格無効のリスクがあります。
- 申請が不安な場合は、公財運行管理者試験センターの支援サービス(約2,930円)の利用も可能です。
講習回数・受講歴のカウント方法を詳しく解説
講習を正しくカウントすることは、資格取得の要件を満たすうえでとても重要です。
平成19年以降、いくつかのルールが明確化・変更されており、要注意ポイントを整理しました。
■ H19年4月1日以前と以降で扱いが異なる要素
- H19以降の講習(基礎・一般)は、同一年度に複数受講しても1回分しかカウントされないルールがあります。
- 基礎講習は必須で、かつその後に一般講習を4回以上受講する形で、合計5回以上になる必要があります。
実務期間と講習の受講タイミングに注意
- 補助者としての実務経験は、基礎講習修了以降からしかカウントされません。
- 講習回数も、実務経験の対象期間に含まれるものだけが有効とされます。
- つまり「基礎講習→実務→一般講習」という順番を守らないと、回数は実質無効扱いに。
年度による巻き戻しカウントの可能性
- H19年制度導入初期には、受講年度が年度始めより前でも「その年度内の講習」としてカウントされる場合がありました。
- しかし同一年度で複数講習を受けても、カウントされるのは1回のみである点も明文化されています。
実務と講習の例:OK/NGパターン
合格の場合
- H19年5月に基礎講習受講
- その後、5年間で一般講習を毎年1回ずつ計4回(年度内重複なし)
この場合、基礎+一般4回で、5回達成として有効になります。
NGの場合
- H19年4月以前に一般講習を繰り返し受講
- H19年に基礎講習受講
- その後、3年間しか一般講習を受けなかった
H19年以前の一般講習はカウント対象外となり、基礎+3回分しかカウントされず、要件不達となります。
資格を目指す人がまずやるべきこと
これから運行管理者資格を目指す方は、試験ルート・実務+講習ルートのどちらでも、最初の一歩として「基礎講習への申し込み」と「実務経験の確保」が鍵になります。
計画的に動くことで、最短最速で資格取得への道を進められます。
基礎講習の申し込みが最優先
基礎講習を受講しないと、試験受験権利も実務カウントも進められません。
多くの講習機関では、ウェブやFAX、電話で簡単に申し込み可能です。
オンライン講習や全国開催もあるため、スケジュール調整もしやすくなっています。
- 講習費:8,900円前後+テキスト送料数百円
- 実施時間:16時間(3日間・1日5〜6時間)
- 全国各地で開講、オンライン対応もあり
補助者としての実務経験を積むには?
試験ルートに進む場合も、補助者ルートを狙う場合も「実務経験」は必要です。
以下の方法で経験を積むのが効果的です。
- 運送会社へ就職:運行管理補助者のポジションを求人で検索(例:Indeed、求人ボックス)
- 派遣経由で勤務:物流系派遣会社で短期補助者業務を経験
- 社内異動や部署変更:トラック運行管理の補佐役として経験蓄積
行政書士事務所の解説では、「補助者として5年以上+講習5回」という実務+講習ルートが認定要件であると明記されています
所属事業所での届出も忘れずに!
また、選任後は毎回の講習受講後にも報告が必要になるので、所属部署・安全管理部門とも連絡を取りながら進めましょう。
スタートダッシュ3ステップまとめ
- 基礎講習に申し込み→受講
- 補助者ポジションで働く(選任届出込み)
- 実務経験と講習回数を年度別に記録・管理
この3ステップをクリアすれば、「試験なしルート」でも最短5年での資格取得が可能です。さらに先は「試験なし取得は可能だが注意も必要」の章で、申請上の注意点へ進んでいきます!
「試験なしで取得」は可能だが注意も必要
試験を受けずに運行管理者資格を取得できるのは事実ですが、「裏技」ではなく合法的な制度に則った方法です。
ただし、申請過程や実務経験の積み方など、ちょっとした不備や勘違いで資格が得られないリスクもあるので、以下の点にしっかり注意しましょう。
裏ワザ的なルートでも申請で不備があるとNG
ブログなどでは「試験を受けなくてもOK」と紹介されることもありますが、実際には実務経験と講習記録を事務局で厳査されるため、書類や証明に漏れがあると不交付になります。
- 特に、「基礎講習」と「一般講習」の回数・年度重複の確認が厳しくチェックされます。
- 講習の日付や証明書の写しが残っていないと、経験や回数が正式に認められません。
- 補助者としての実務経験も、選任届出+所属証明がきちんとされているかが問われます。
資格取得後の届出や管理責任も忘れずに
運行管理者になったあと、会社では選任届と再選任届を運輸支局へ提出し続ける義務があります。
また、資格は一度取得すれば終わりというわけではありません。
- 一般講習を2年ごとに受け続ける必要あり
- 転職・支店移動時の届出(再選任・住所変更)が必要です
- 放置すると「資格保有している=運行管理者」としてルール違反の状態になってしまいます
運行管理者として求められる実務の理解が必要
講習や実務経験を積んだだけではなく、現在進んでいる業務内容や法律・ルールの運用を理解しているかも重要です。実務を知らない状態で資格を取ってしまうと、現場でのミスや事故につながる恐れがあります。
資格はあくまで「スタートライン」であり、実力を備えてこそ意味があるということは、意外と見落としやすいポイントです。
よくある質問Q&A
試験なしルートで運行管理者資格を目指す方から、よく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。
- 本当に試験を受けずに資格が取れるの?
-
国家試験に合格しなくても、
- 補助者として5年以上の実務経験と
- 基礎講習+一般講習(合計5回以上)をクリアすれば、試験なしで資格者証の交付が可能です。
ただし、講習の年度内回数制限や証明書の不備があると、不交付となるリスクもありますので注意が必要です。
- 講習だけ受ければ自動的に資格が取れるの?
-
講習だけでは取得できません。
「基礎講習」「一般講習」を受けるだけでは不十分で、補助者としての実務経験(5年以上)との組み合わせが必須です。
講習は講習で、実務経験は実務経験で、両方が揃ってはじめて資格申請の要件を満たします。 - 何年以内に講習を受ければ有効ですか?
-
講習は「基礎講習を修了後にカウント開始」され、かつ「同一年度内に複数回受講しても1回分としてカウント」されます。
講習と実務経験は該当年度内にしっかり記録を残し、期限や回数を間違えないように注意してください。
了解しました。以下が簡潔なまとめ文になります。
運行管理者の情報収集や失敗しない転職のコツ

運行管理者の実際の給料や年収、募集要項などもっと詳しい情報が見たい、もしくは実際に転職を考えている方は「エージェント」の利用がおすすめです。
転職に関しても最近の運送業界ではエージェントからの転職が主流になってきました。
しかし数多くの運送会社がある中で、自分に合う会社を探すのは至難の業です。
なのでプロのアドバイザーに相談しながら情報収集や転職を進めたほうが安心です。
運送業界でおすすめのエージェントは「リクルートエージェント」です。
業界最大手で求人数や実績において群を抜いてトップのエージェントです。
リクルートエージェントでは
- 給料や年収
- ボーナスや退職金
- 詳しい仕事内容
- 勤務時間
- 年間休日
- 勤務地
などの情報をゲットできます。
>>リクルートエージェントで運行管理者の詳しい情報をゲットする
そこがリクルートエージェントの最大のメリットです。
- 希望の労働時間は○時から○時まで
- 給料は手取りで40万円以上欲しい
- 土日祝日は休みたい
などの要望をアドバイザーに伝えると企業と交渉してもらえます。
いちいち自分で面接に行って確認する必要がなくなりかなり楽です。
つまり自分の希望が納得できる段階で面接を迎えることができるということです。
交渉が苦手な人、面倒くさい人には嬉しいサポートです。
また大手や人気の運送会社は非公開求人になっているケースが多いです。
これは企業が採用情報をあまり外部に漏らしたくないのと、エージェントからの紹介者のみに対象者を絞って対応の手間を省きたいからです。
リクルートエージェントは非公開求人数が日本一なので、あなたの希望する運送会社が隠れているかもしれませんね。
登録方法は簡単で料金は一切かかりません。
登録したからといって絶対に転職しないといけないわけではありません。
アドバイザーとしっかりと相談しながら自分に合った企業探しや情報収集をしましょう。
まとめ:試験なしでも取得は可能、ただし正しい手続きが必要
運行管理者の資格は、試験を受けずに取得できるルートが正式に用意されています。
補助者としての実務経験と講習受講が条件ですが、書類やカウント方法など細かいルールがあるため、誤解や申請ミスには注意が必要です。
「試験なし=抜け道」ではなく、あくまで正規の取得方法のひとつ。
制度を正しく理解し、確実な手続きを行うことが成功のカギとなります。